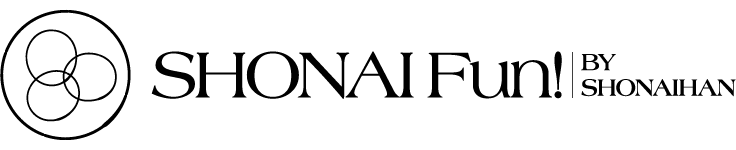思い出がつまった大切な場所
「小さい頃はザリガニ釣りとかしてたんですよ。」と語るのは酒井家第19代であり致道博物館の副館長酒井忠順さん。
酒井さんから2冊の冊子をいただいた。ひとつは庄内藩の歴史などを綴った「故(ふる)きを温(たず)ねて」、もうひとつは「新しきを知る」。ご本人が庄内藩の歴史をまとめ書き綴ったものだ。
何気なく「新しきを知る」をパラッとめくった。歴史建造物とともに、幼い頃の酒井さんの夏休みの思い出や、刀剣女子によって行列ができたエピソードなど、ユーモアたっぷりに描かれている。「こんな楽しみ方もアリなんだ」と、かな〜りリラックスして歴史に立ち向かうことができそうだ。
とくに、致道博物館にある旧鶴岡警察署庁舎について「ウェッジウッドブルー」と表現されていたページがあり、この響きがなんとも素敵で強く印象に残り、改めて致道博物館とともに庄内藩の歴史に触れてみたいと思った。

擬洋風建築、多層民家、赤門、御隠殿…
バラエティ豊かな歴史建造物!

「旧鶴岡警察署庁舎」は遠くからでもよく目立つ。2013年から修復がはじまり、明治時代に建設された当時の色を再現、2018年にリニューアルお目見えとなった。
修復以前は白で、その色に慣れていたイチ市民としては当初かなり唐突感があったけれど、今となっては陽に照らされた青も、青空に溶け込むような青も、雨に濡れた青も素敵だなと思う。他の地域に擬洋風建築の建造物はあるけれど、この色は他にはなかなかないと思う。
警察というからには、取り調べ室が2部屋もある。身分によって使い分けされていたそう。2階のバルコニーからは市内も一望できて、ちょっと特別感。刀剣の展示時期にはここで刀剣女子たちがよく写真を撮っていたっけ。どうやったら上手く自撮りできる?教えてほしいよ。
ここだけをぐるぐる回って、映えスポットを探してしまいそうになるけれど、せっかく来たので敷地内の建物も堪能してみる。

同じく目をひくもうひとつの擬洋風建築は「旧西田川郡役所」。手前の広場ではお弁当を広げたり、子どもたちが自由に遊び回ってもいいそう。酒井さん、少年時代は木登りも楽しんでいたのだとか。そんなことを聞くともうすぐ2歳になる息子を連れてきたかったと思う。今はいろいろ踏んづけるのがブームだから、ちょっと不安だけど。
「旧庄内藩主御隠殿」には歴史展示や中庭を鑑賞できる広い奥座敷が広がる。展示品で気になったのは一本の長〜い釣り竿。一般的には接木で作られる釣り竿だけど、苦竹を使用して一本の竿にした。釣りを奨励していた庄内藩では釣りが上手いと出世ができたそう。



広い奥座敷では、窓から見える一枚絵のような中庭を眺めながら、ごろんと寝っ転がっている人もいるんだとか。ちなみに酒井氏庭園は国指定名勝に指定されている。なんて贅沢なお昼寝!奥座敷では子ども向けに論語の素読を定期的に開催中。素読は藩校だった致道館で奨励していた学習法のひとつだ。

「訪れた人たちにも良き思い出の場所となるようにしっかり守りたい」
北前船や職人用具などが展示された「民具の蔵」、「重要有形民俗文化財収蔵庫」には当時実際に使われていた「ばんどり」などを展示している。「ばんどり」は装飾が細かく、庄内藩の豊かさや美意識を教えてくれるよう。






華やかな装飾の「祝いばんどり」など、見比べるのも楽しい


朝日地区田麦俣の民家を移築した「旧渋谷家住宅」。茅葺き屋根の虫を炙り出すために冬場は実際に囲炉裏に火をつける。それにしてもこのお宅、農家出身の私からみても、当時にしては大きな住居だと思う。豪農だったのか。



酒井さん、新しい企画もアリですか?

建築から興味を持って見学した致道博物館。幼児教育に興味津々の新米ママとしては、今度は論語や徂徠学など、勉学の視点から学んでみたい。歴史っていろんな角度から楽しめるのが面白い。と新たな気づきがあった。
そして巨大鬼ごっこ、素読&ピクニック、擬洋風建築で写真撮影イベントなど、勝手にイベントを脳内コラボレーション。そしたらもっと歴史がワクワクと身近なものに感じられそう。「続・新しきを知る」がスタートしたあかつきには、そんなイベントレポートも書き綴ってくれるかな、酒井さん。
基本情報
名称/致道博物館
営業時間/3月〜11月:9時〜17時(最終入館16時30)、12月〜2月:9時〜16時30(最終入館16時)
休館日/年末年始、12月〜2月の水曜(展示替のため、一部休室になることあり)
入館料/一般800円、高・大学生400円、小・中学生300円、団第割引あり
アクセス/JR鶴岡駅から車で6分
ホームページ/https://www.chido.jp/